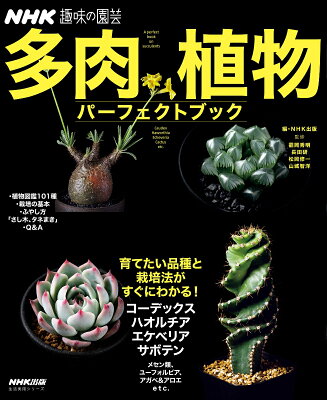近年ますます人気が高まっている「多肉植物」。その中でもひときわ目を惹く存在が『斑入り品種の多肉植物』です。
多肉植物はもともと、独特な色形や種類の豊富さなど多彩な魅力を持つ植物ですが、なかでも「斑入り品種」はその希少性や唯一無二の美しさで、多くの愛好家の心をつかんでいます。
この記事では、そんな斑入り多肉植物の基礎知識をはじめ、斑の種類や魅力を豊富な実例写真とともにご紹介。
さらに「購入時に気をつけたいポイント」など、はじめての方にも役立つ情報をわかりやすくまとめましたので、ぜひお役立てください!












様々な斑入り多肉植物の種類と「斑(ふ)」の基礎知識
世界に一万種以上も存在するといわれる多肉植物。
そのなかでもとりわけ目を惹くのが、葉や茎に美しい色彩の変化や模様を見せる「斑入り種(ふいりしゅ)」です。
ハオルチアの「モルドール」(左)という品種と、その斑入り種「モルドール錦(ノリ斑)」(右)

上記のように、斑入り種の流通名には元の品種名に「~錦(にしき)」と名が付けられている場合が多く、英語表記の「f. variegata/variegated (斑入りの)」をもじって通称「バリエ/バリエガータ」と呼ばれることもあります。
■ そもそも「斑入り(ふいり)」とは?
→ 葉っぱの一部に葉緑体が少ない、または全くない部分がある状態のこと!
「斑入り」とは、植物の生長に欠かせない“光合成”を行う器官である葉緑体(ようりょくたい:緑色の部分)が、何らかの原因によって部分的に欠乏し、葉や本体の一部が「白や黄色、赤」など通常とは異なる色味になる現象・状態を指します。

緑一色のものと比べて爽やかさや華やかさがアップすることに加え、斑の入り方にも個体差があることで特別感が生まれ、多くの人を惹きつける魅力となっています。
「なぜ斑入りになるのか」はまだ完全には解明されていませんが、「葉緑体を作る・維持するための遺伝子の異常」や、「強い光・高温・薬剤・ウイルス感染」などの外的要因や環境ストレスによって、細胞に変異が生じることが原因のひとつと考えられています。


また、斑入り種には、「自然発生して増殖された普及種」から「突然変異などによって偶然生まれた希少個体」、近年では「人工的な処理で斑を作り出したもの」まで、さまざまなタイプがあります。
斑の入り方や色の違いによって、それぞれにユニークな名前が付けられているのも大きな特徴です。
いろいろな斑入りの多肉植物と斑の種類(名称)
ここからは、いろいろな種類の斑入り多肉植物と、多肉植物によくみられる斑の種類(呼び名)について、いくつかの切り口からご紹介していきます。

1.斑の分布からみる
…外斑(覆輪斑)、中斑、片斑、全斑(お化け)
斑が葉や植物体のどの位置に現れるかに着目した分け方です。
● 外斑(覆輪斑)…葉の縁に沿って斑が入るパターンです。
外斑(そとふ)と覆輪斑(ふくりんふ)は同じものを指します。アガベやアエオニウム、エケベリアなどによく見られ、斑の入り方は固定化されているものが多いです。






● 中斑(なかふ)…葉の中央部分に斑が入るパターンです。
こちらもアガベやアエオニウムなどによく見られ、斑のパターンも固定化されているものが多いです。






● 片斑(かたふ)…株を左右に分けるかのように片側にはっきりと斑が入った状態を指します。
サボテンやハオルチアなどによく見られます。生長に従って斑と葉緑体部分の割合・バランスが変化することもあります。






● 全斑(ぜんふ)…成長点(株の真ん中)を含む全体に、葉緑体がほとんどもしくは全く無い状態を指します。
株全体が真っ白や薄黄色に見えることが多いです。通称「お化け」や「ちょうちん」とも。






全斑の状態になるとほぼ光合成ができないため、親から株分けなどで離された単独個体では長く生きられない場合がほとんどです。
栄養をくれていた親株が枯死したため、ゆっくり枯れていったお化けの子株 (ハオルチア マリン錦)




2.斑の形状からみる
…縞斑、スジ斑、ハケ斑、ノリ斑、かすり斑
斑がどのような形で現れるかに着目した分け方です。
● 縞斑(しまふ)・スジ斑…葉の付け根から先端に向かって直線的な斑が入るものです。
縞斑とスジ斑の明確な区別は定められていないようですが、一般的に「縞斑は比較的はっきりとした帯状の斑が入るもの、スジ斑はそれよりも若干細めでやや不規則な斑が入るもの」を指す印象です。
特に縞斑は葉緑体部分のコントラストが目立ち華やかな個体が多いです。アガベやハオルチアなどをはじめ、様々な多肉植物で見られます。






● ハケ斑(刷毛斑)…ペンキを乾いたハケでサッとひと塗りしたような、やや不規則でリズム感のある斑が入るものです。
こちらも明確な定義はありませんが 、ハケでザっと撫でたような若干細かめの斑が入るものを指すことが多いです。
模様は固定化されておらず、同じ株でも見る方向によっては随分雰囲気が違ったりすることがあります。






● かすり斑…かるく表面を削ったような、細かく不規則な斑が入るものです。
ややザラついた質感に見えることも。サボテンやハオルチアなどの一部で見ることができます。ハケ斑などと一緒に表れることも多いです。


● ノリ斑…株もしくは葉の大部分を覆うように斑が入るものです。
株の地肌がまるでクリームなどでコーティングされたような雰囲気を持ちます。株の表面に斑の層があることでそのように見えるそうです。
見た目は「全斑」とかなり似るものもありますが、葉緑体がほぼない全斑と比べ、ノリ斑の葉の裏や内側には葉緑体の層が残っており、生育には問題がない場合が殆どです。






ノリ斑はその美しさや希少性から、一部の品種ではオークションなどで高値が付くことも多いです。
「全斑」と「ノリ斑」の混同に注意!
【その見分け方】
とくに近年「ハオルチア」は、流通時に前述の「全斑」とこちらの「ノリ斑」が混同されて販売されているケースが増えています。しかし、もともとこの二つは価格や将来性が大きく異なるため、購入時にはぜひしっかりと確認をしましょう。
・ 全斑…全斑の窓の色は、地色の明るさを少し抑えたような落ち着いた色合いで、窓と地肌との境界がやや分かりにくいのが特徴です。
・ ノリ斑…ノリ斑の窓は地肌に葉緑素が残っている影響で、地色とコントラストのある青灰色やグレーがかった色に見えます。
両者は光の加減で非常に似通って見えることがあるため、色々な角度からよく観察して見極めてくださいね。


3.斑の色合いからみる
…黄斑、キサンタ、白斑、赤斑
斑がどのような色をしているかに着目した分け方です。
● 黄斑…薄黄色もしくは濃いクリーム色がかった色合いの斑です。
葉緑体のなかの葉緑素(緑色部分●)が部分的に少ない場合の色合いです。比較的多くの多肉植物で見ることができます。






● キサンタ変異体…株全体が均一に黄色に変色する状態を指します。
「黄斑」が一部の範囲に現れるのに対し、「キサンタ」は株全体が黄色〜淡い黄緑色に変色するのが特徴です。
これは、葉緑体のなかで緑色の色素を含む「葉緑素●」の生成が、遺伝的あるいは突然変異によって全体的に不十分となるためです。その結果、同じく葉緑体内に存在する「カロテノイド(黄色~橙色●)」の色が相対的に強く表れ、全体が黄色く見えるしくみです。


キサンタは、一般的にはいわゆる「斑入り」とは異なる位置づけですが、色の変化の成り立ちや性質に共通点があることから、広い意味では斑入りの仲間とも考えられます。
通常個体や他の斑入り種に比べてデリケートな場合が多いため、やや注意して栽培する必要があります。
●白斑…白~純白の色合いの斑です。
葉緑体のなかの「葉緑素●」も「カロテノイド●」もほぼない場合の色合いです。斑の部分が多いほど、光合成ができないため成長が遅くなります。
前述の「全斑」の多くは葉緑体のほとんどが失われているため、実質的にほぼこの白斑の状態になります。


●赤斑…赤味の強い色合いの斑です。
「アントシアニン色素(赤紫色●)」が多く含まれることでこのような色味になるそうです。
季節や用土のpHによって若干赤味の濃淡が変化することもあります。






4.斑の変化特性からみる
…季節斑、曙斑、後冴、固定斑
斑の変化に着目した分け方です。
●季節斑…特定の季節にのみ現れる斑や、季節によって色や模様が大きく変化する斑を指します。
例えばセダムの「オーロラ(虹の玉の斑入り種)」は、普段は緑がかったカラーですが、冬季になると鮮やかな桃色に変化します。
また一部のアガベなどでは成長開始の季節にのみ、成長点部分に斑が入る品種があります。(成長とともに元の緑色に変わっていきます)。






●曙斑(あけぼのふ)…成長の初期段階にのみ斑の要素を持つものを指します。
季節斑にも似ますが、こちらは季節を問わず、成長点付近に斑が入るという特性を持つものです。
育つごとに、斑だった部分はゆっくりと地色の緑色に近づいていきます。この「成長初期の葉の明るさ」を「曙(夜明けの明るさ)」に見立てたネーミングとなっています。






またその逆で、上記右の画像のように「後から遅れて斑が鮮明になる『後冴(のちざえ)』」という斑の入り方もあります。
これらは遺伝的な特性によるもので、曙斑は「葉緑体の発達が遅く、内部の葉緑素が遅れて生成されるため」・後冴は「生長とともに葉緑素の分布や細胞構造が変化するため」、そのような状態になるのだそうです。
「曙斑」と「薬剤処理の苗」の混同に注意!
一部の多肉植物には、販売促進のため成長点付近だけ薬剤で色を抜いて販売されているものがあります。
この場合、一見「曙斑」と見分けがつきにくいことがあります。
薬剤で色を抜いたものは、時間が経つと徐々に全体が元の地色に戻ったり、成長点が傷ついて弱ってしまった場合には最悪枯れてしまうこともあります。
「生長点の色が抜けている=曙斑」とは限りませんので、購入の際は品種名などをあらかじめ調べて確認するようにしましょう。
●固定斑…斑の模様や色、入り方が遺伝的に安定しており、それが子株にも同じように引き継がれる性質をもつものを指します (=変化があまりない斑)。
長期にわたって安定した斑が維持されるため、園芸品種として名づけが行われ、繁殖されて広く流通するのが一般的です。






※ 次項で、斑のバランスや均一性の美しさを表す「極上斑」という呼び名が登場します。この固定斑もいわば極上斑ではあるのですが、そもそも固定斑は斑の均一性や安定性を大前提とするため、あえて「極上斑」と表現をすることはありません。
5.斑の品質(鑑賞上価値)からみる
…極上斑、派手斑、地味斑、微斑、斑落ち
斑の入り方の美しさやバランス、または均一性といった鑑賞上の価値に着目した分け方です。
特に多肉植物のなかでは、斑の入り方の変化やバリエーションが多いハオルチアなどでよく使われます。
(以下はすべてその「ハオルチア」を例にご紹介します。)
● 極上斑(ごくじょうふ)…ほとんどの葉にバランスよく斑が入っており、非常に安定感のある美しさを持っているもの。
株全体を眺めた際の斑の分布の安定感、斑と緑色部分のコントラストやバランス感などが優れているものを指します。
品種にもよりますが総じて希少性が高く、オークションなどでも高価になる傾向があります。

● 派手斑(はでふ)…それぞれの葉に広く斑が入り、非常に華やかに見えるもの。
斑のバランス/安定感は極上斑ほどではありませんが、斑の部分が多く見た目に華やかなものを指します。
こちらもオークションなどで高値になりやすいですが、成長点に斑が多いと将来的にお化けに近づいてしまう可能性もあるため注意が必要です。


● 地味斑(じみふ)…斑はいくつか容易に確認できるものの、華やかさは少なくやや落ち着いた印象のもの。
見た目の派手さはさほどありませんが、子吹きを待ったり葉挿しや交配に使うことなどを考えると、このくらいの斑の分量の方がいずれも良い成績を残しやすい印象です。意外とおすすめゾーンです。

● 微斑(びふ)…全体の1~2割程度もしくはかろうじて見つけられるくらい微かに斑が入った状態のもの。
斑は入っていないかと思っていたら「あった、うれしい…!」となるくらいの微量も含みます。
斑の葉を含む位置で胴切りを行うと、斑の入った仔株が出て斑の更新・継続ができる場合もあります。

● 斑落ち(斑ぬけ)…元々は斑入りだったが、育てているうちに斑が消えてしまった状態のもの。
元々斑入りの性質を持つ株(=斑の遺伝子を持つ株)は、斑が消えても遺伝的に不安定さが残ることがあります。
そのため、胴切りなどの作業によって、再び子株に斑が現れる場合もあります。こうした特性や販売時の混乱を避けるために、品種名だけでなく、斑落ちという「由来」をあえて明記することがあります。

ひとくちメモ
■よく使われる「斑まわり」ってなに?
「斑まわり(ふまわり)」とは、斑入り植物における斑の入り方やそのバランス、株全体の斑の安定性などの良し悪しを総合的に判断・表現する際に使われている言葉です。
現在の見た目だけでなく、その斑が将来的にどのように変化しそうかを判断するニュアンスも含むのが興味深いところ。
例えば「この苗斑まわりいいね」「だよね、今後が楽しみ!」/「斑まわり悪くなってきた…」「胴切りしてみたらどう?」など、その良し悪しは単に斑の状態だけでなく、その株への期待や落胆を暗に含むのがこの言葉のおもしろい部分です。
「多肉植物の斑入り品種と斑の名称を写真で紹介」まとめ
多肉植物の斑入り種は、同じ株でも葉ごとに表情が異なったり、育てる環境や年数によって色や模様が変化したりと、眺めるほどに新しい発見があるのが魅力です。
今回ご紹介したように、外斑・ハケ斑・全斑・ノリ斑など、斑の入り方や呼び名もさまざま。それらが複合して現れることも多いため、それぞれが異なる美しさと個性を持ち、見ていて飽きることがありません。
ただし人気が高い一方で、薬剤による人工的な斑や、デリケートで栽培が難しいタイプもあるため、入手時には品種名や株の状態、育てる環境との相性をしっかり確かめておくことが大切です。
いろいろな写真を通じて、多肉植物の斑入りがもつ奥深い美しさを感じていただけたら嬉しいです。
ぜひお気に入りの一株を見つけて、日々の暮らしに彩りを添えてみてくださいね!
次回は、そんな斑入り品種を長く楽しむための「育て方のポイント」について詳しくご紹介します。どうぞお楽しみに。